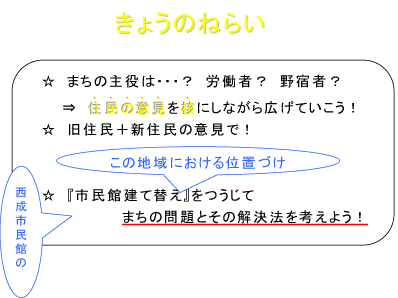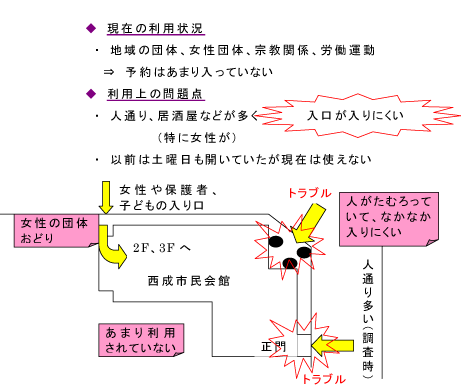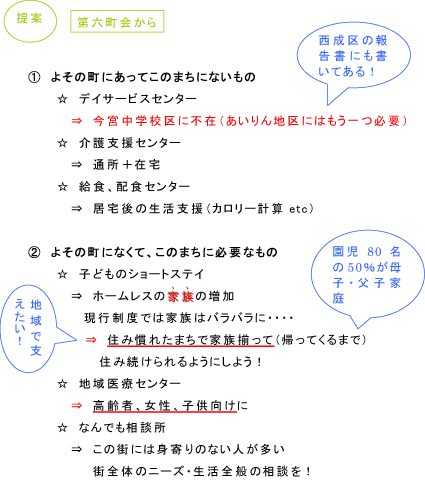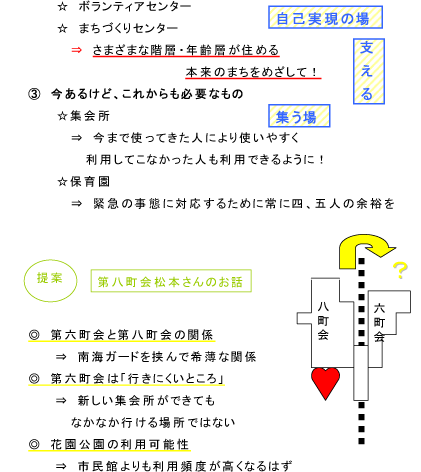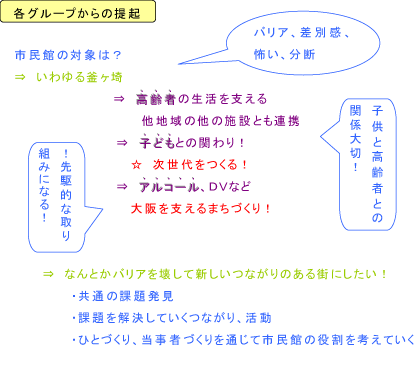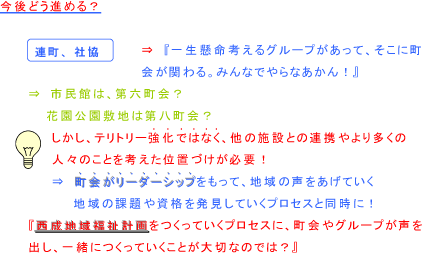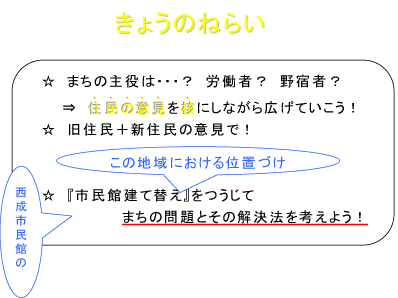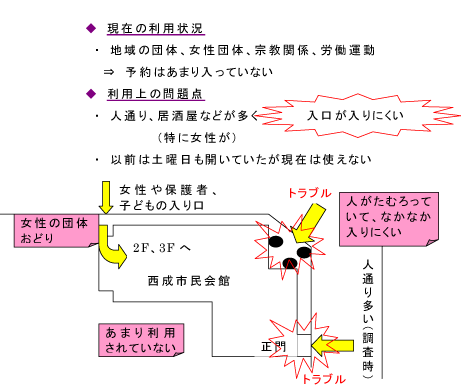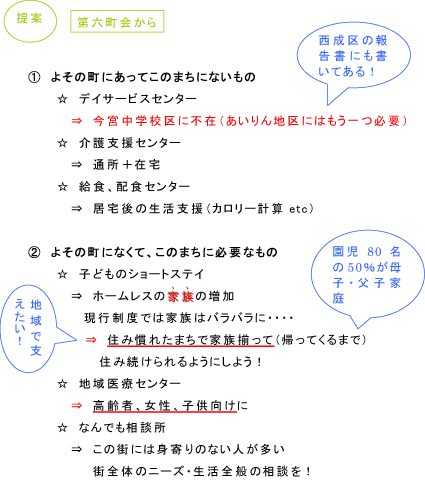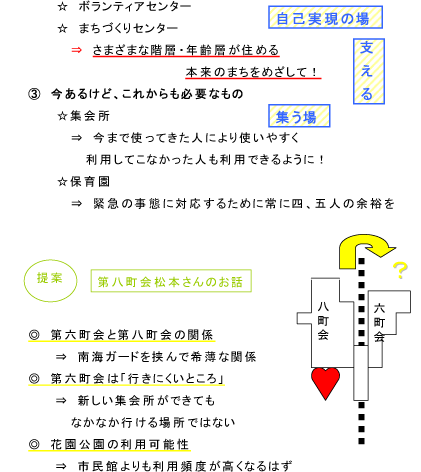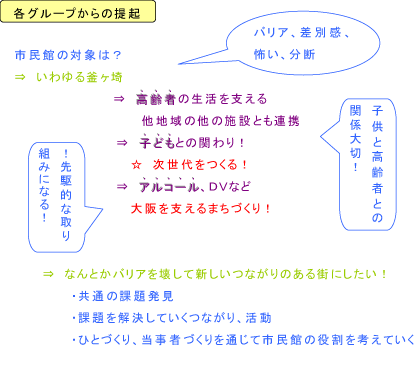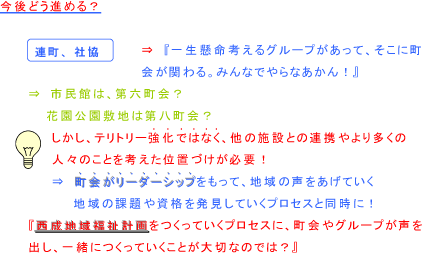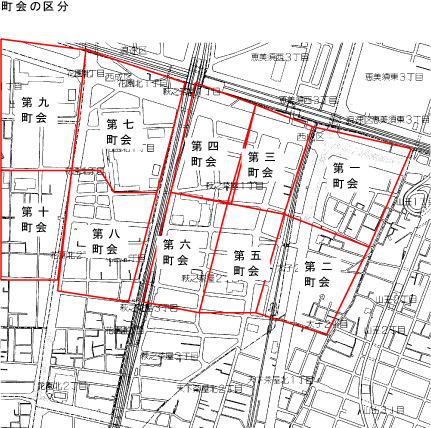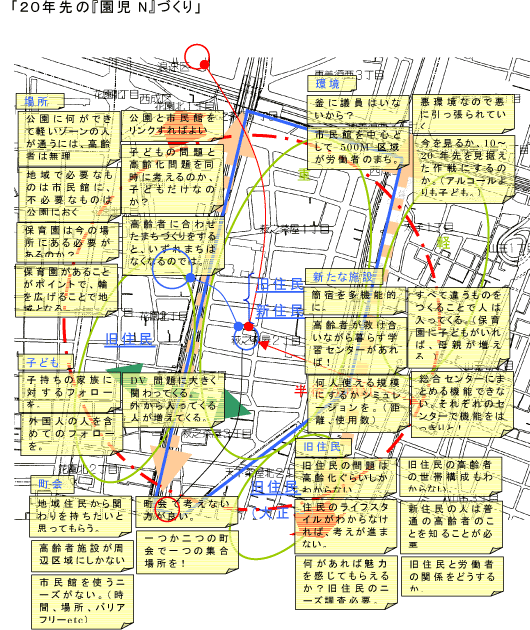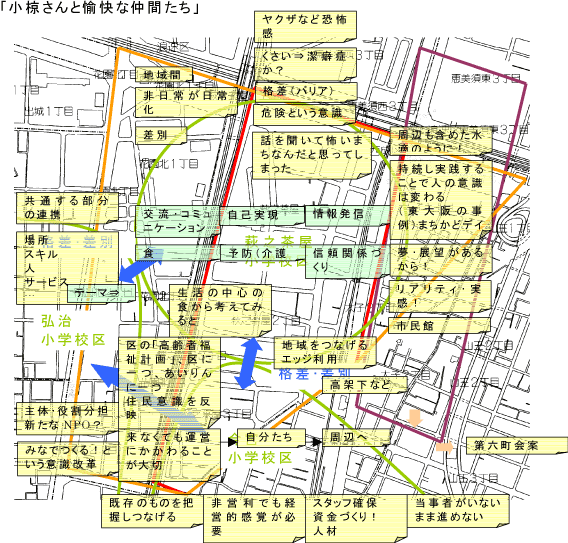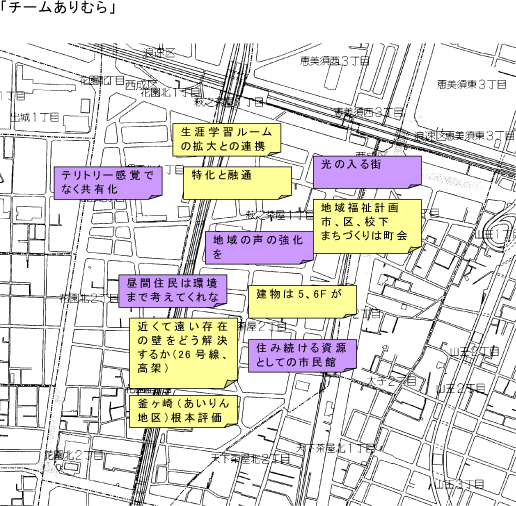<もしも西成市民館を建替えるとしたら?>
2001.6.30 ワークショップその1
2002.11.23 ワークショップその2(ダイジェスト版)
もしも西成市民館を建替えるとしたら?その2(詳細)
ワークショップ記録 2002,11,23
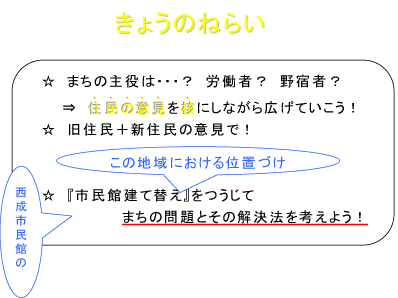
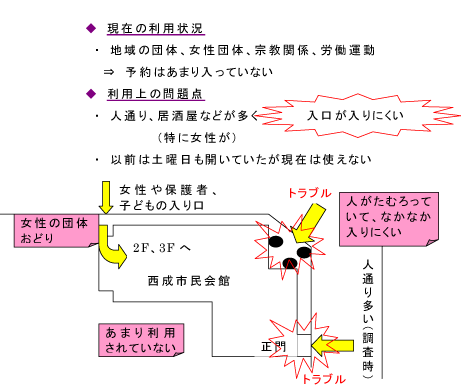
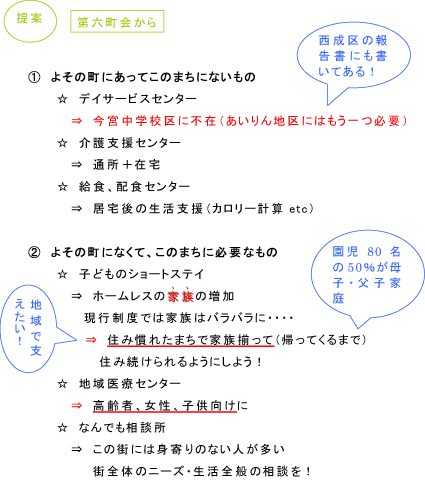
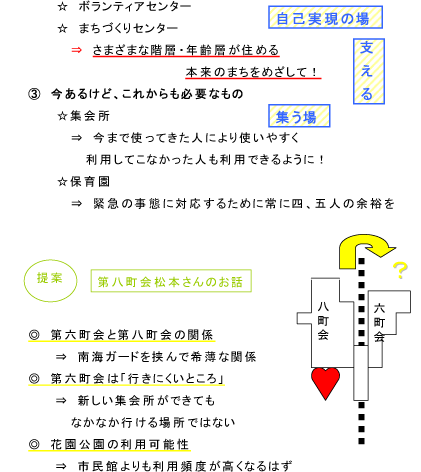
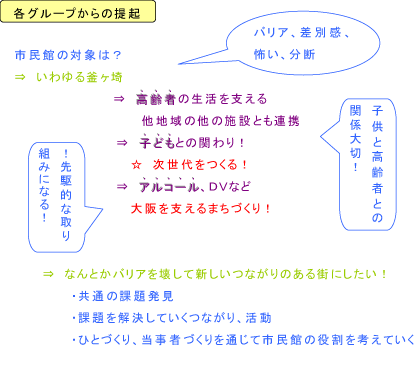
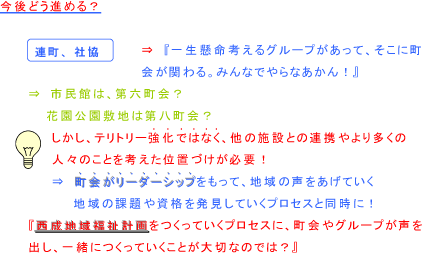
保育園に来る子供たち
- 「あいりん地区」外こどもたちが80%
- かつて住んでいて外に出ても、生活のあり方、今までのつながりから、「わかくさ保育園」を選ぶ人も多い!
- まったく関わりがなくても選ぶ人が3割いる。
- いわゆる「あいりん」に閉じない位置づけを持っている。
- この地域や地域内の施設は実は、開かれている!
- 関わりをもっている!
- もっと声を届けたいために第六町会をつくった。
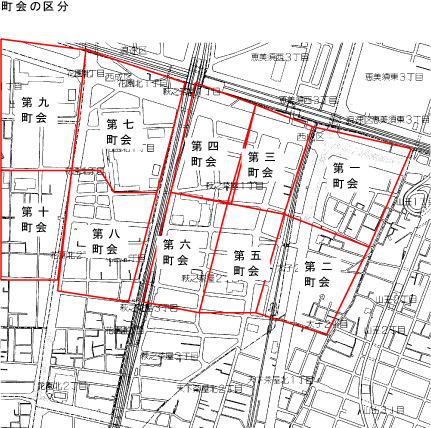
チームディスッカッション 「20年先の『園児N』づくり」
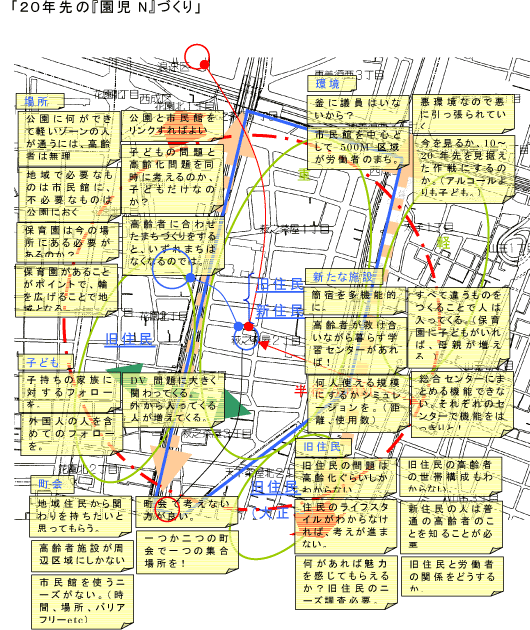
- 釜ヶ崎に住む子供と家族
子供のいる家庭、外国人の家庭に対するフォローが必要だ
DV問題に大きく関わっている
保育園があるということが大きなポイント、そこから輪が広がっていく
高齢者中心のまちづくりだと将来住人のいないまちになる
- 釜ヶ崎の環境
議員がいない
現状をみるか10〜20年先を見据えた作戦にするか
(アルコール問題よりも子供)
市民館を中心として半径500メートル以内が労働者の街
悪環境なので悪に引っ張られていく
- 西成市民館の場所
公園に何ができるか。隣接する地域の人、高齢者が行きづらい
釜ヶ崎内で必要な施設は市民館の中へ
その他の地域(住民でなくても)でも必要な施設は駐車場などを利用してつくる
公園、市民館をリンクさせる
保育園が現在の場所であることが必要なのか
子供問題、高齢者問題を一緒に考えてよいのか
- 旧住民
もともと住んでいる人の世帯構成、ライフスタイルがわからない
高齢化
普通の高齢者を知ることが重要
旧住民と労働者の関係をどうするか
何があれば魅力あるまちなのかニーズ調査が必要
- 新たな施設
全く違うものを造ることで人が入ってくる
何人使える規模にするのかシュミレーションする(距離・使用数)
高齢者が助け合いながら暮らす学習センター
それぞれの福祉機能を明確にすることが必要
- 町会
町会で分けて考えないほうがよいのかも
1つか2つの町会ごとに集会所を造る
現在の市民が使いにくい(時間・場所・バリアフリーの問題など)
周辺の区域にしか高齢者福祉施設がない(釜ヶ崎にない)
ディスッカッション 「小椋さんと愉快な仲間たち」
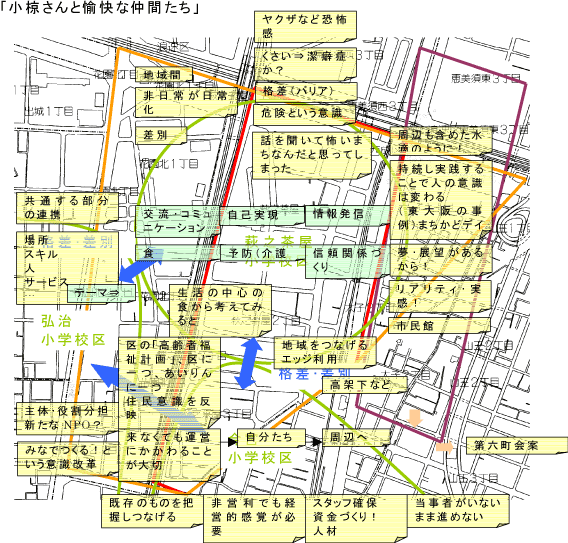
テーマ・・・場所・スキル・人・サービス・食から生活を考えてみよう
↓
交流(コミュニケーション)・自己実現・情報発信・食・予防(医療介護)・信頼関係づくり
- 交流(コミュニケーション)
「話を聞いて怖い町なんだと思ってしまった。」
地域間の格差
やくざなどへの恐怖感
臭い
危険という意識
差別
持続し実践することで人の意識は変わる
↓
水滴のように周辺地域に広がる
- 自己実現
夢・展望未来がある
リアリティー実感!
- 情報発信
地域をつなげるエッジ利用(高架下など)
既存のものを把握し、つなげる
- 信頼関係づくり
みんなでつくるという意識
意見を聞く当事者(住民)がいないままでは進めない
住民が運営に関わることで周辺地域へ意識を広げる
共通する部分の連携
↓
地域間の非日常が日常へ
- 市民館の運営
非営利でも経営的な感覚が必要
スタッフ確保、資金作りと人材
地域住民が関わりたいと思えるような関係をつくる
チームディスカッション 「チームありむら」
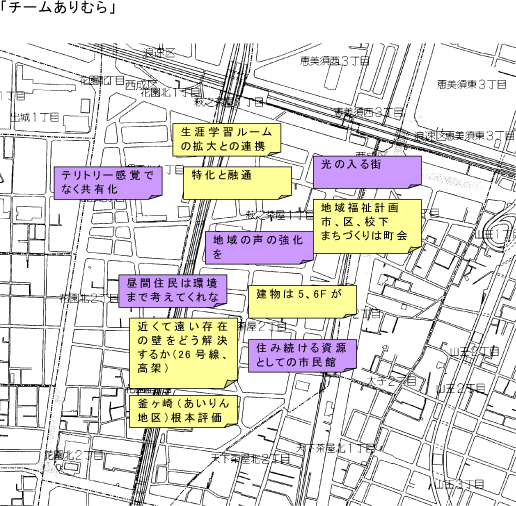
テーマ・・・
- 釜ヶ埼(あいりん地区)の根本評価
- 近くて遠い存在の壁をどう打ち砕くか?
- 生涯学習ルームの拡大と連携
- 特化と融通
- 住み続ける資源としての市民館
↓
- 光と緑のある街
今の釜ヶ埼のまちには光がない、そして、緑がない
光が入り、緑に囲まれた町づくりをめざそう!
- 地域福祉計画を踏まえた提案を
現在ある生涯学習ルームをもっと開放し高齢者も交えた交流の場
- まちづくりは町会、そして校区、区、市へ拡げたい
第6町会にだけでなく周囲との連携を深め、テリトリー感覚ではなく共有化をめざす
- 昼間住民は環境のことまで考えてくれない・・・
地域の声を強化し自分の言いたいことが言い合える場が必要
- 市民館は5〜6階建てがベスト!